「ダメ、絶対!」路線は、かえって回復をさまたげる。
ジャーナリストのマイア・サラヴィッツさんがいっています。
かつて麻薬依存だったサラヴィッツさんは、依存症は禁止の強要ではなく、他者とのつながりで回復に向かうと主張してきました。
今回のコラムで、自分はワインもマリファナもたしなむと吐露しています。そういう「完ぺきを求めない」生き方が、回復を維持するのでしょう(I’m in Addiction Recovery and I Still Drink Wine. By Maia Szalavitz. Aug. 14, 2025. The New York Times)。
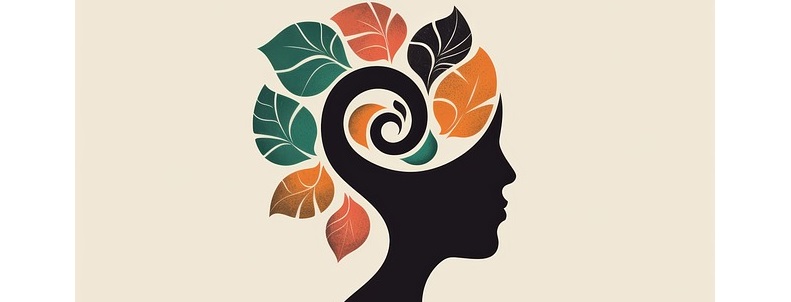
ヘロインなどの麻薬依存から回復するには、強い意志で麻薬を断ち切らなければならないという「常識路線」が、トランプ政権下で強まっている。けれどそれでは依存症は救えないとサラヴィッツさんはいいます。
「薬物依存からの回復に必要なのは、なぜ薬物を使うか、理由を知り、その代わりを見つけることだ。私は、自分はだれも愛することができず、人とつながれないという思いから麻薬依存になった」
重度のうつ状態で麻薬に依存したサラヴィッツさんは、自助グループや抗うつ剤を使うことで依存症から抜け出しました。
回復に向かって、気づいたことがあります。
自助グループでは、すべての薬物が禁止だったけれど、あれはなんだったのか。
「私が参加した回復プログラムは、絶対に薬物にもどってはならないと指導し、精神科の薬までも「安易な、弱い道」とみなしていた。けれど自分は抗うつ剤でマイナスを脱している。薬物を禁止するのではないところで、多くの回復は実現している」
いまではワインも飲むようになり、眠れないときはマリファナのグミを使うようになった。ワインは2杯半を超えない抑制ができている。

サラヴィッツさんは、いったん薬物依存になったら一生薬物を遮断しなければならないという考え方に強い疑問を呈します。薬物依存者がアルコールを飲めば、依存がぶり返すというような見方は偏見だともいう。
依存は、一度起きたからといって、一生くり返されるわけではない。だれもが依存になるわけでもないし、だれもが依存から抜け出せないわけでもない。肝心なのは、なぜその薬物を使うのかという問いかけだとサラヴィッツさんはいいます。
「ダメ、絶対!」というような断固とした言い方は意味がない。
麻薬も覚醒剤もアルコールも、またギャンブルも、ダメだという前に「なぜ」を考えなければいけない。精神科では、「断固とした意志」なんてまぼろしです。
(2025年8月22日)
