2週間ほど前、精神分析の本を1冊、読み終えました。
『人はみな妄想する』という、松本卓也さんの著作です。
400ページ以上の学術書だから、読みとおせる自信はなかった。でも書いた松本さんが抜群に頭のいい人なので、しろうとのぼくにもわかる部分が多々ありました。何がわかっていないかをわからせてくれる、ありがたくも刺激的な著作でした。
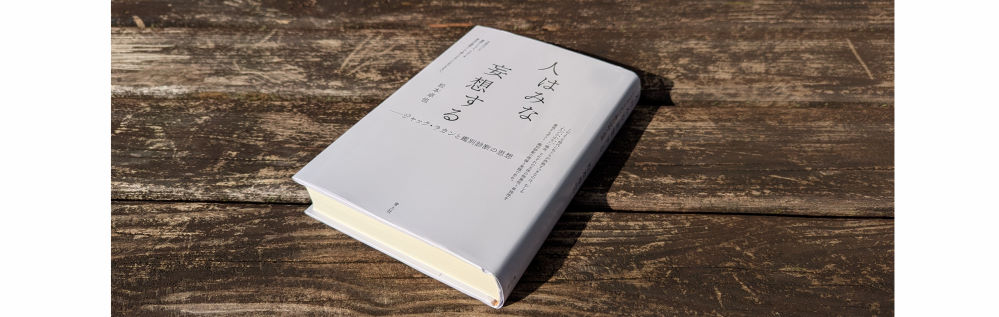
そのうえで、印象に残ったところ、考えたところをメモしたい。
と考えつつ、それでいいのかと自問する。
『人はみな妄想する』は、ジャック・ラカンの理論について書いた本です。
フランスの哲学者で精神科医でもあったラカンは、精神分析をめぐる難解な理論で知られます。専門家ですら容易に把握できないラカンの理論を、ぼくが理解できたなんていえるはずがない。理解していないのに書くのは、詐欺のようなものではないか。
その一方で思います。
精神分析の理論は理解できなくても、それが臨床でどう実践されているかは、実感をもってわかる部分がある。そうなんだよなと、うなずく記述が随所にありました。そのことについては書けるのではないか。なぜなら肝心なのは臨床であって、精神分析も理論も、あくまで臨床とともにあるべきだからです。
ラカンの理論がどれほど深遠でエレガントでも、臨床で生かされなければ意味はない。
ぼくの知っている臨床、つまり精神障害者の思いと暮らしとから、逆にラカンの理論を照射することができるのではないか。妄想ともいえる思いを抱きながら、ぼくは『人はみな妄想する』についての考察を、断片的な直感にすぎないけれど試みてみます。

たとえば、「ラカンの理論なるものは存在しない」という指摘について。
理論なるものが存在しないというのは、ラカンの理論は確固たるひとつの体系ではなく、時代とともに変わってきたという意味です。松本さんはそのことを「ラカンの理論をひとつの「理論なるもの」として読解するのではなく、複数の学説がせめぎあいながら展開する理論的変遷として読解すること」だといっている(34)。
ラカンは自らの理論に固執せず、時代とともに変化させてきた。それは理論が脆弱だったからではなく、精神病という現実の前にくり返し変容を迫られたからではないか。変容することで、ラカンは精神病のなかにさらに深く分け入ろうとしたのではないか。だとするなら、変容はつねに臨床から離れないラカンの倫理でもあった。
松本さんの記述を追いながらぼくはそんなことを考えました。
脈絡のないメモをつづけます。
(2025年3月31日)
