『人はみな妄想する』は、松本卓也さんによるジャック・ラカン読解の切り回しがみごとで、いろいろなことを考えました。最後の方ではラカンとフェリックス・ガタリが対比され、とくに興味を引かれます。
ガタリは早くからラカン精神分析の限界を指摘していました。
「・・・実践的な限界としては、マイノリティとしての精神病者を精神分析の埒外に置き、精神分析をブルジョアジーの嗜みへと矮小化してしまう恐れがある。ガタリはその点をすでに六六年に批判していた」(384)
精神分析は金持ちの余暇であってはならない。権威や権力に敏感だった“革命家”ガタリらしい指摘です。
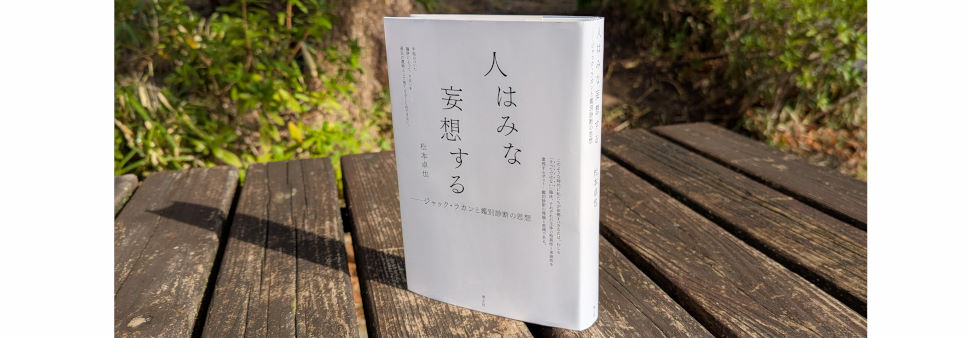
より本質的なのは、精神分析は固定的なものではないという観点でしょう。一人ひとりに特異な「狂い」があり、それを突きとめるのが精神分析だというラカンの思想は、人間存在を固定するかのようでもある。そうではない。その人自身も、その人を取りまく状況も、つねに変化する動的なものだというのがガタリの思想でしょう。
「ガタリがラカン・・・より優れていた点があるとすれば、それは革命の可能性、すなわち私たちが今まさに生き、行動している際に生じている因果性を変えることを考えようとしたところにあるだろう」(389)
私たちが生き、行動するさいの因果性は、私たち内部の無意識に規定されると精神分析はいいます。その無意識を、ガタリは個人のなかに閉じこめない。もっとずっと広く、社会や政治、権力関係によっても規定されると考える。無意識は集団的なものであり、かつ「不断に更新していくような終わりなき運動」として開かれている。

とまあ、こんなふうに書くとぼくがラカンやガタリを理解したかのようだけれど、そうではない。松本さんの著作を読み、いやながめ、浮かんだ想念の断片です。
ただぼくのなかには、こうした想念が現実の精神病とどうつながっているか考えたいという思いがずっとあります。フロイトからラカンへ、精神分析から今日の精神医療へという流れのなかで、精神病の一部はそれなりに対処されるようになったかもしれない。けれどそのほかの精神病、ことに統合失調症は、いまだに謎のままではないか。
「分析主体は、普遍的な構造には決して回収できない」(406)
狂気は知に回収されることなく、つかみきれない謎として人間存在の背後に立たずんでいる。それは分析の対象ではなく、逆にぼくらが狂気から分析される対象ではないか。そんなイメージがぼくのなかには浮かびます。
(2025年4月7日)
