双極性障害で、14年間“プロの精神病患者”だったにもかかわらず、薬をやめ健康になったローラ・デラノさんの記事を、前回このブログで紹介しました(3月19日。The New York Times, March 17, 2025)。
精神病の患者や元患者が助け合い、薬をやめる潮流はメインストリームの精神科医も動かしています。そのひとりがイギリスのマーク・ホロウィッツ医師です。
ホロウィッツ医師は自身がうつ病で、15年にわたりレクサプロという抗うつ剤を服用していました。しかしデラノさんのような元患者のサイトを見て、抗うつ剤をやめています。もちろん彼らの支援を受け、手順を踏んだうえで。
精神科医の自分が、患者グループに助けられている。
「専門家って誰のことか、ですよね。私は博士の学位を持ち、抗うつ剤も熟知しているのに、患者仲間の支援がなければ薬をやめられなかった」
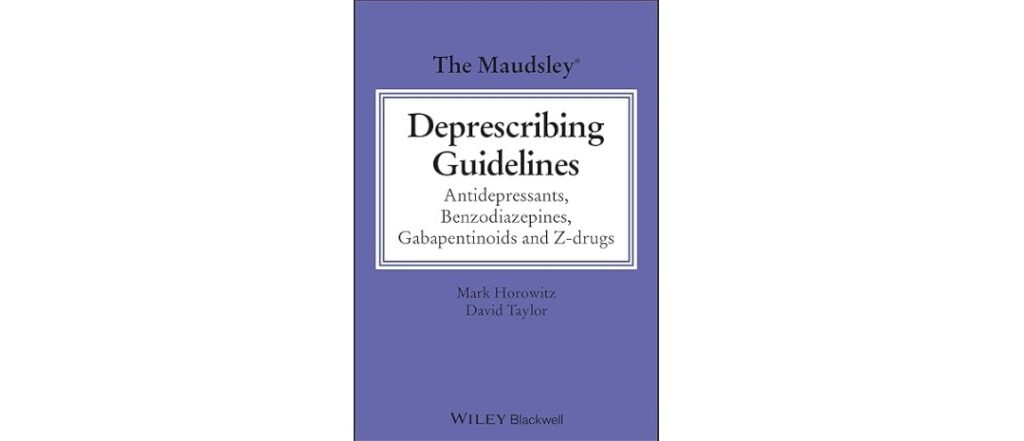
ホロウィッツ医師は自身の経験から、精神科の薬をやめるガイドラインを作りました。
『モーズレー薬剤離脱ガイドライン』(The Maudsley Deprescribing Guidelines。表題は拙訳)は、主として抗うつ剤からの離脱方法を説いたものですが、この本でいちばん大事なのは、精神科の患者は薬剤を処方してもらうだけでなく、その薬剤から離脱することもまた「患者の権利」だとされていることでしょう。
権威あるイギリスの医療保険ガイドラインにも去年、はじめて「薬をやめることについて」の一章が登場しました。イギリスの精神科医はこのガイドラインにしたがい、患者に抗うつ剤を処方するだけでなく、減薬や服用の中止も進めることになります。

巨大製薬企業が支配するアメリカでも、兆候は出てきました。
アメリカ精神医学会の研究部門は、薬剤からの離脱について指針を出すつもりだと担当部長のジョセフ・ゴールドバーグ医師はいいます。
「製薬産業は、薬をやめることについては何もいわない。この問題はほかのグループに話を聞くしかない」
頼りになるのは、当事者である患者や元患者だということでしょう。
いま起きている議論の中心はうつ病や不安障害、双極性障害などです。おなじ精神病でも、統合失調症については安易な断薬ができないとされる。けれどぼくは、これもまた製薬企業とその手のひらに乗った精神科医がつくる偏った言説ではないかと疑います。いまの精神医療はあまりにも生物学と薬理学に支配されすぎている。人間の本性に深くかかわる精神病は、それよりさらに広い視野のもとで捉えるべきではないか。
そんなことを、このあともさらに考えていきます。
(2025年3月21日)
