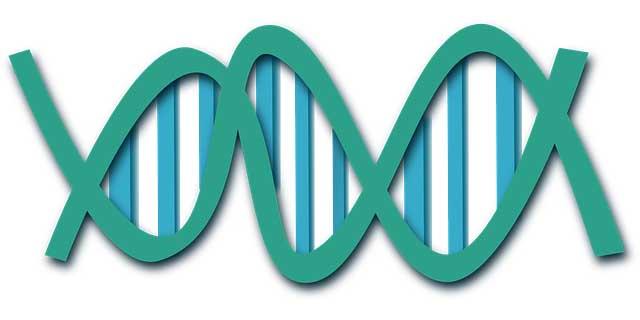体外受精はここまで来たかと、進歩に驚きます。
今回はイギリスで、「3人の親」から体外受精で「ひとりの子」ができました。
史上初の「3人親」体外受精は、2人の親の遺伝子DNAと、3人目の親の「ミトコンドリア遺伝子DNA」が使われています。本来の親は2人だけれど、3人目の親の遺伝子があってはじめて可能になった体外受精でした(Eight healthy babies born after IVF using DNA from three people. 16 Jul 2025. The Guardian)。

ミトコンドリア病という遺伝病の対策です。
ミトコンドリアは生物の細胞内にあって、細胞にエネルギーを供給する重要な器官です。細胞1個あたりに数百のミトコンドリアがあり、そのなかにはミトコンドリアDNAと呼ばれる、細胞核とは別の小さな遺伝子があります。この遺伝子に異常があると、ミトコンドリア病という遺伝性の難病になる。
「3人親」の体外受精を受けた親たちは、そのままでは生まれてくる子どもがミトコンドリア病になる確率が高かった。ニューキャッスル大学のダグ・ターンブル教授らは、その対策を長年研究してきたといいます。
今回ターンブル教授らが行ったのは、体外受精でできた受精卵(胚)から細胞核を取り出し、それを3人目の、正常ミトコンドリアをもつ親の受精卵(胚)に注入するという技法でした。これで、受精卵は正常なミトコンドリアとともに発育します。
これまでに4人の男の子と4人の女の子、合わせて8人がこの体外受精で生まれ、さらにひとりの妊娠が進行中です。いずれもミトコンドリア病はないと医学専門誌NEJM(New England Journal of Medicine)に報告されました。

ミトコンドリア病は新生児5千人に1人ほどのまれな病気ですが、原因が複雑で、症状も発達障害や神経障害など多彩です。診断はむずかしく、実際の患者は報告よりも多いといわれ、早期に死亡するケースもあります。
治療法はなかったけれど、少なくとも一部のミトコンドリア病は、これで治療への道筋が開けました。この治療法はMDT、ミトコンドリア寄付療法(Mitochondrial donation treatment)と名付けられています。
体外受精で人間の遺伝子を操作することは倫理的に認められていませんが、イギリスは2015年に法律を一部改正しました。今回は核ではなく、ミトコンドリアの遺伝子“操作”だったので問題ないとされたのでしょう。
生命科学の輝かしい成果ではあるけれど、それはまた「生まれる前に遺伝子を調べる」技術の進歩と一体でもある。光とともに、影の部分もまた強まっていると懸念します。
(2025年7月23日)