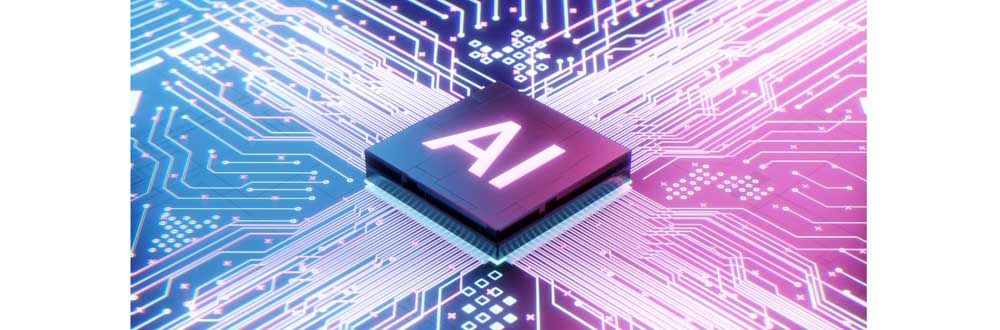デジタル技術を使っていると、認知症になりにくい。だから高齢者はスマホやパソコンを使っていたほうがいいと、前回書きました。でも認知症になったら、スマホもパソコンも使えないからお手上げじゃないか。
そう思っていたら、そんなことはない。「AIコンパニオン」というのがあると聞きました(Could Dementia Patients Benefit from an A.I. Companion? July 31, 2025. The New York Times)。
対話型ロボット、ではありません。
対話型のアプリです。それも、アマゾンの「アレクサ」が世間話をする程度ではない。AIコンパニオンは、軽度から中度の認知症患者の「認知機能の維持」に特化したアプリです。デジタル・ベンチャー企業のニューデイズ社が開発しました。
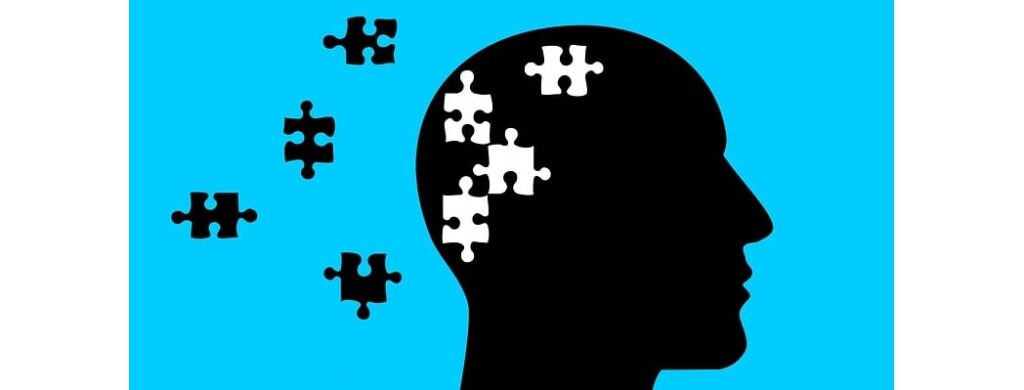
AIコンパニオンは、パソコンの前にいる認知症患者に話しかける。パソコンにはウェブカメラがあり、インターネットにつながっているので、患者はネットの向こうにいるAIコンパニオンと会話を進めることになります。
AIは患者の生活史を熟知し、特定のことばや文章をはさみこみながら、患者の話に合わせて反応する。むかしの記憶を呼び起こしたり、感情を刺激して対話をつづけることで、認知能力の低下をふせぐことができるとニューデイズ社はいいたいようです。
アプリの基礎となったのは、ハーバード大学の神経学者、ヒロコ・ドッジ博士らの研究でした。
認知症は治療できないけれど、適切な刺激があれば認知機能のおとろえを遅らせることはできる。そのためには専門家が注意深い対話をくり返すことが効果的だと、ドッジ博士らは186人の認知症患者を対象とした実験で確かめています。
実際にどうやって「注意深い対話」を進めるのか。
認知症患者と対話ができる専門職はかぎられ、その費用もばかにならない。ニューデイズ社のAIコンパニオン・アプリは月間99ドル、これで認知能力の維持、活性化ができるなら、人手不足とコストの問題は解決できるかもしれない。

専門家のなかには、これで認知能力が維持できるかどうかは疑問とする見方もあります。しかし別の専門家は、AIコンパニオンが刺激的な会話をもたらし、「生活の質」が向上するなら意味はあるといいます。本人だけでなく、家族や介護者も助かるでしょう。
5年前なら、こんなものは「子どもだまし」だった。でもAIは急速に進化している。いまならありかも、という気がします。AIコンパニオンは対話相手というより、ぼく自身の記憶、自分史の保存者としての「もうひとりのぼく」になるかもしれない。それなら、将来消えかけているぼくの支えになってくれるでしょう。
(2025年8月27日)