AI、人工知能について、二つの論考がありました。
トーマス・フリードマンさんは、AIはぼくらの生活に大変革をもたらすといいます。一方ゲリー・マーカスさんは、AI競争はから騒ぎだといいます。すれちがう二つの論をどう読めばいいか、迷います(The One Danger That Should Unite the U.S. and China. By Thomas L. Friedman. Sep 2, 2025. The New York Times)。
ニューヨーク・タイムズのコラムニスト、フリードマンさんは、かねてから元マイクロソフト社の戦略調査責任者、クレイグ・マンディーさんを取材してきました。専門家ではないけれど、専門家の考えを熟知している。そのうえで、AI開発は飛躍的に増大する「規模の法則」に従っているといいます。
「電子回路が増大し、つぎ込むデータが増大し、電力が増大し、巨大思考のためのアルゴリズムがあれば、どこかの時点で思考の飛躍、創造性、問題解決能力が出現する」
未来のAIは、ちょうど乳児が言語を獲得するように、巨大な回路と情報の環境下で自然に学習し、自立する「超頭脳」として生まれる。
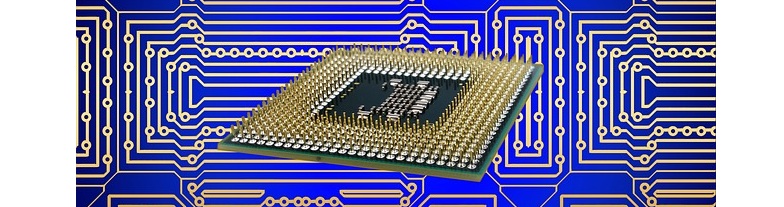
新世代のAIは、放置すれば悪用される。そうならないよう米中両国が連携すべきだといい、そのためのさまざまな方策を提案しています。
たしかにテロリストや詐欺師、陰謀論者がAIを自由に使えれば、地球規模の破滅も起こしかねない。米中がそれぞれのAIを敵対させるのではなく、相互に認識可能な基盤のうえに築けば、破滅は避けられるかもしれない。傾聴すべき提案です。
一方、ゲリー・マーカスさんは、「超頭脳」はかんたんにはできない、いまのAIブームはから騒ぎといいます(The Fever Dream of Imminent Superintelligence Is Finally Breaking. By Gary Marcus. Sept. 3, 2025. The New York Times)。

マーカスさんはニューヨーク大学の名誉教授で、ゲオメトリック・インテリジェンスというAI企業の創設者でもある。最新のAI、「チャットGPT5」を見ても以前のものと大差なく、競合する他のAIも似たりよったり。大規模路線は頭打ちで、「規模の法則」なんて存在しないといいます。
無尽蔵に集積回路を集め、莫大な電力で駆動すればいつかどこかで超頭脳、スーパーAIができるなんてことはないというのですね。
いまの異常なAI投資ブームは、一時的な熱狂にすぎないのか。
AI競争も、それに引きずられているアメリカ経済も、そのアメリカに引きずられている日本も、架空のバブルに踊っているだけなのか。そこはかとない疑念が生じます。
(2025年9月5日)
