フェリックス・ガタリの『分子革命』を読みました。
きわめて難解で、いつものように読んだというよりながめたといったほうがいい。
付箋を貼りながらひとまず読み通したけれど、何もわからない。それでしばらく放置し、付箋を貼った部分を中心に、あらためてメモを取りながら読み直しました。ようやくおぼろげにわかった気が、少しだけします。
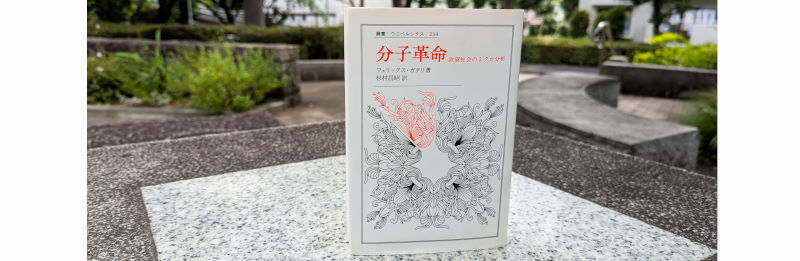
本の全体はわからない。部分的にわかる、というか触発される表現がある。そのひとつが、以下の1行でした。
幸福の実践はそれが集団的であるとき体制を転覆するものになる。(原文傍点付き。p113)
イタリアの自由放送局「ラジオ・アリーチェ」の1977年放送の一部だと脚注にあります。このことばに共感したガタリが、自著に残したのでしょう。
ぼくも、この一文に共感します。浦河的だなと思いながら。
同時に、現実はこうならないという諦念がある。ぼくはこれを、自分のなかでこう読み替えました。
革命を夢見るのであれば、集団的な幸福の実践をめざすことだ。

革命、集団、幸福、実践。
ここにはガタリという存在の核心にふれる概念が凝縮されている。幸福の集団的実践? それが革命になる? 不可能でしょ、という思いと、しかしそれを求めてやまない強度と過激さと。
ガタリは精神医療、精神分析、社会闘争の実践家であり、人間が「歴史の主体」になり、「生を変えること」に「あいもかわらぬ夢想」を抱きつづけていたと、盟友のひとり、モーリス・ナドーは追想しています。
そういうガタリの全体像を知らないまま、ことばじりをとらえて語るなんてことが許されるだろうか。哲学の素養のないものが、彼の思想を感覚的、刹那的に「理解」したなどといってもいいものだろうか。
そういう思いはあるけれど、ぼくは自分がガタリに誘われている、挑発されているという思いが消えません。まるで妄想にとりつかれたかのように。
なぜそんな妄想にとりつかれるのか。なぜ妄想を語りたくなるのか。
人をそうさせるのがガタリだということについて、さらにあれこれ考えてみます。
(2025年7月7日)
