精神病はぼくらに何を問いかけているのか。
去年からこのテーマに引きこまれ、あてのない読書をくり返しています。
宇野邦一さんの『ドゥルーズ 流動の哲学』(増補改訂版)を読み、読みながらつくったメモを読み返して、また少しだけ「わかった気分」になりました。
精神病、とくに分裂症が、現代思想の中枢にいすわっている。
それが何か言い当てることはできないけれど、言い当てることがができないという、そのことについて考えつづけるのが、根源的に重要ではないか。
それこそが、精神病の、分裂症の問いかけではないのか。
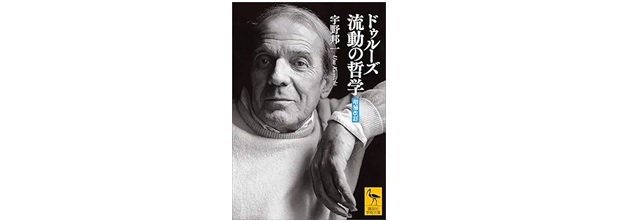
宇野邦一さんによれば、哲学者のジル・ドゥルーズは自身の哲学について、「理解すること」より「使用すること」のほうが大切だといっていたそうです。
「全体を相手にする必要はなく、必要に応じて断片を扱うだけでいい。そんなイメージを、ドゥルーズは思想を「理解する」のではなく、「使用する」こととして提唱しているのだ。ときに「工具」を用いるように、と比喩的に語ったこともある」(『ドゥルーズ 流動の哲学』p25)。
伝統的な西欧の知をはみ出した哲学。哲学以前の、考えることを徹底的に考えたところで現れる思考。そんなドゥルーズの思想は、ぼくなどが理解できるものではない。それでもいい、好きな部分を好きなように使えばいいといわれると、なんだか解放された感覚になります。
しかも、「精神病は本質的に医学の外部にかかわる」などという記述を見つけると。
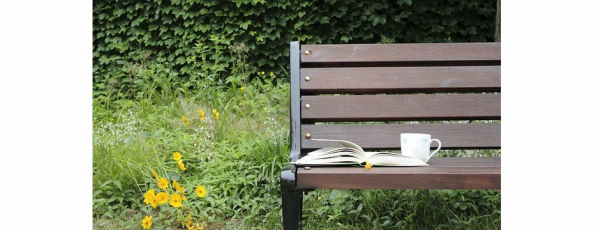
「精神の病が発生することは、この社会の集団、家族、関係のあり方に、ひいては政治にも資本主義にも密接にかかわっている」(p149)。
宇野邦一さんは、ドゥルーズがフェリックス・ガタリと書いた現代思想の金字塔『アンチ・オイディプス 資本主義と分裂症』を論じるなかで、ドゥルーズ=ガタリにとって分裂症は治療すべき病気ではなく、「分析の原理」であり、「方法」であったといっている。
分裂症が現れる社会は、支配と抑圧を構造化している。さらにそれをまた構造化している政治や経済、歴史がある。分裂症をとおして、この世界がわかるという意味でしょう。
けれどそんな「理解」は、しろうとの迷走と笑われるにちがいない。ドゥルーズ=ガタリの思想は広大無辺で深甚なもの、分裂症も精神分析も、辺縁であり余談にすぎないと専門家はいうでしょう。
それは承知の上で、ぼくはつづけます。ガタリを、ドゥルーズを、全体ではなく、自分の目に止まった好きな部分から読むスタイルを。彼らの思想の断片を、分裂症者の暮らしの情景のなかから読み取とろうとする作業を。
(2025年8月11日)
