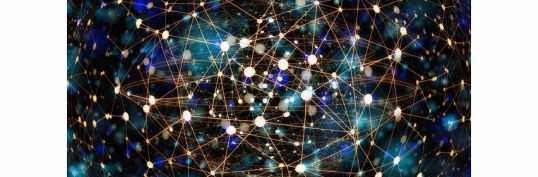ジャンクフードは、食べすぎると健康をそこね、身体をおかしくする。おなじように、ネット依存も精神をそこね脳をおかしくするのではないか。
ネットは脳のジャンクフード。わかりやすい議論です。
ジャンクフードよりさらに深刻かもしれないと、コラムニストのメアリー・ハリントンさんが書いています(Thinking Is Becoming a Luxury Good. By Mary Harrington. July 28, 2025. The New York Times)。
100年前にIQテスト(知能検査)が発明されてからずっと、人間の知能は向上してきた。ところがいまこの傾向が反対になっている。OECD各国でおとなのIQは低下し、低所得層で顕著だ。専門家は、スクリーンタイム、スマホの影響と見ている。
多くの人はネットの娯楽コンテンツを衝動的に消費し、ネット依存になっている。なかにはフェイクや敵対的なニセ情報、さらに最近ではAIがつくる映像があふれ、脳がジャンクフードを食べつづけているような状態になる。
これを懸念するエリート階級や宗教団体、保守層は、デジタルの使用を自制するようになった。子どものスマホを制限し、家政婦を雇うときにはスマホを使わないと誓約させ、スマホを禁止する私立学校を選んでいる。
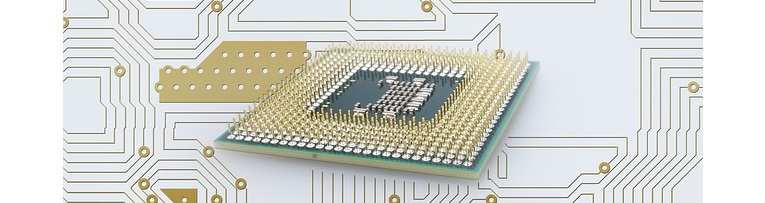
「ポスト・リテラシー」の時代は、「ロングフォーム・リテラシー」を獲得するものとそうでないものの格差が拡大するとハリントンさんはいいます。
ロングフォーム・リテラシーとは、“深思考”とでも訳せばいいのでしょうか、長文の複雑な論文や小説などを読み解く力です。生まれつきの能力ではなく、努力と長時間の学習で習得される。深思考で脳は発達し、左脳の分析的な活動が活発になり、集中力と論理的な思考が身につく。これはネットの娯楽的な利用では習得できない。

ポスト・リテラシーは、リテラシー、ものごとを「読みとる」力がないか、なくてもいい人たちが大部分となった時代をさすのでしょう。ネットとデジタルが支配する21世紀は、そういう時代になっている。
これまで格差といえば経済的な差でした。これにいま、「考える力」の格差が生まれている。ロングフォーム・リテラシーの少数者と、ポスト・リテラシーでもいい大多数の人びと。その思考力の格差です。
善悪ではなく、一人ひとりの自由な選択の結果でもある。
問題は、ポスト・リテラシーのもとで世界的にポピュリズムが勢いを増し、民主主義が失われていることでしょう。ぼくは自分にどれだけ考える力があるかはわからないけれど、ポスト・リテラシーの世界をどう生き抜くかは考えつづけたい。
(2025年9月12日)