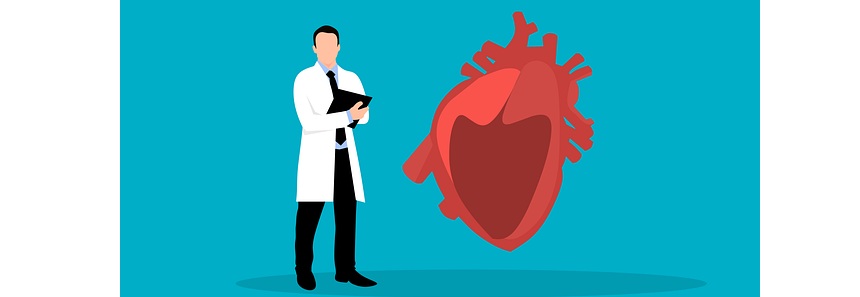臓器移植を進めるために、死の定義を拡大すべきだという主張があります。
心臓が止まり、死亡宣告が行われた患者に特別な処置を施すと、移植のために提供される臓器を保護することができる。こうすればいまよりずっと臓器移植は進むだろう。そのためには、死の定義を拡大する必要があるといいます。
アメリカでの話ですが、いずれ日本でも議論になるでしょう(Donor Organs Are Too Rare. We Need a New Definition of Death. By Sandeep Jauhar. July 30, 2025. The New York Times)。
人が死んだかどうかの判定は、きわめて厳密に行わなければならない。まちがいは許されませんから。
今日、死は、脳か心臓が全面的に機能を停止し、元にもどることはないと医師が判定した状態をさします。医学的に見ると、脳死と心臓死のふたつがあることになる。実際にはほとんどが心臓死で、脳死は例外的です。そのわずかな脳死者のなかから、本人家族の了解があって臓器提供が行われるのはさらに少数です。だから臓器提供は例外的で、移植を必要とする人の多くが臓器の提供をえられないまま亡くなっている。

これに対し、脳死ではなく、心臓死した人の臓器を使おうとする研究が進んできました。
NRP、常温局所灌流(normothermic regional perfusion)と呼ばれる方法です。
これは、心臓死した人の特定の臓器について、心臓が止まったあとも血流を確保し、その臓器を良好な状態に保つ医療技術です。
従来、心臓死した人の臓器は、血流の停止でほとんどが移植に使えない状態になっていました。けれどNRPを施せば移植できる良好な状態を保てます。問題は、このような措置を施すと、いったん止まった心臓が動き出す可能性もあることです。
一般人の感覚では、いったん止まった心臓が動き出したら「生き返った」ことになる。でも医学的な死に変わりはない。ここは法律できちんと決めておかなければなりません。

ニューヨークの心臓専門医、サンディープ・ジャウハー博士ら移植医療に携わる専門家は、NRPを実施できるよう法的な整備を求めています。
「臓器移植を望みながら亡くなる人は毎日15人もいる。厳しい倫理基準をみたしながら、移植に使える臓器を増やすことを考えなければならない。最新の技術は合法的なものだ。われわれは死の定義を拡大しなければならない」
NRPは、すでにヨーロッパでは実施している国があるそうです。だからアメリカでも認めてほしいという議論は、これから広がるでしょう。その議論はいずれ、生命倫理にかんしてつねに西欧を追ってきた日本にも及ぶでしょう。
(2025年9月19日)