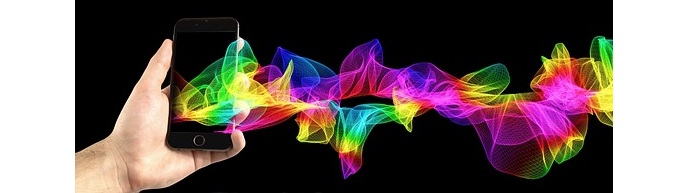毎日のように新しいスマホが登場する。新しいアプリが現れる。
ほとんどは無視するけれど、無視するだけでは社会生活ができない。近所のスーパーで買い物をするにも、クレジットカードに「ひもづけ」されたスマホが必要です。きのうはポッドキャストのアプリでもがきました。若者には何でもないことだのに。
新幹線も飛行機もスマホで予約、購入です。銀行も、パソコンではなくスマホに替えるよう圧力をかけてきます。
もうパソコンに安住していられない。さらに“スマホ化”しなければなりません。
ところが、しょっちゅうやり方がわからない。途方にくれる。あきらめかけたころにようやくわかる。そのくり返し。なんでこんな苦労しなきゃいけないのか。投げ出したくなったり、イライラ、おろおろしたり。
便利なのはありがたい。けれどときには重荷です。

そこで、認知行動療法を心がけるようになりました。
デジタル社会に「追いつくため」ではなく、自分の「脳を鍛える」ためにイライラおろおろする。そう考えるとスマホは老化防止の脳トレーニングです。重荷ではなく、むしろありがたいと多少は積極的に取りくむことができる。
老人医学は、高血圧などいくつかの「危険因子」が認知症の40%に関係しているといいます。しばらく前の記事ですが、「危険因子」を低減するためとして、以下のような項目があがっていました(17 Ways to Cut Your Risk of Stroke, Dementia and Depression All at Once. April 23, 2025. The New York Times)。
・飲酒をしないか、適量にとどめる
・脳の認知機能を使う。
・野菜や果物、魚やナッツなどを取り入れた食生活
・中から軽度の運動
・人生の目標があること
・広範な社会的つながりを持つこと

「脳の認知機能を使う」ためには、「ちょっとむずかしいこと」をするよう専門家はアドバイスしています。読書やパズル、新しい道具の使い方を学ぶのもいい。それをだれかといっしょにするとなおいい。会話が生まれ、つながりが増える。
その意味で、スマホはいい道具です。わからないと文句をいいながら家族に、仲間に、使い方を聞く。わからなくてもできなくてもいい。困ってあがく、その過程が大事です。周囲とかかわっていれば、詐欺にもあわなくてすむだろうし。
(2025年10月13日)