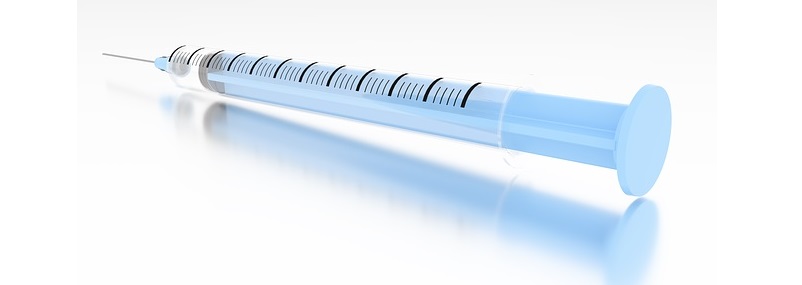依存をめぐる議論が微妙に変化しています。
かつて断定的だった議論が、よりニュアンスを帯びたものになっている。科学的には望ましい方向だけれど、一般社会にはますますわかりにくくなっています(Rethinking Addiction as a Chronic Brain Disease. Sept. 3, 2024. The New York Times)。
アメリカのある空港に、こんなポスターが貼ってあったそうです。
「依存は選択ではない、誰にでも起きる」
依存症になる人は、自らの意思でそうなっているわけではない。誰にでも起きることだという意味です。依存症への偏見をただし、治療をうながすために作られたキャンペーンのポスターでした。こういうポスターが必要なほど、依存症への偏見は強い。

またこれが議論の分かれるところでもある。
依存は選択ではないという言い方は、依存は脳の慢性的な病気だという、いまの精神科の主流の見方を反映しています。がんやアルツハイマー病のように避けることのできない病気だから、本人のせいではない。
けれど、病気だといいきるのも問題だという異論が出ています。たとえばジョンズ・ホプキンス大学のクリステン・スミス博士。
「慢性的な病気だというと、まるで変えることができないかのようで、希望がない」
スミス博士は、依存を“脳中心”で見ることを批判します。
なぜ薬物を選ぶのか。それはなにかから逃れようとするからかもしれない。壊れた家庭、隠れた精神疾患の存在、学習障害、いじめや孤立。そういった社会環境にもっと注目すべきだ。何世代にもわたる依存があることは、遺伝的要素への見方を広げるだろう。

(Credit: DEA, Openverse)
そういうスミス博士自身、かつては重度のヘロイン依存症でした。1日4回の注射を4年つづけ、刑務所で服役し、それから大学で学位を取得している。麻薬をやめられたのは、中産階級のしっかりした家庭があったからだといいます。
治療を受けなくても依存症から抜け出せた自分は、「脳の慢性疾患」ではない。
依存が病気だということは、偏見への対策として必要かもしれない。けれどせめて「治療可能な病気」としてはどうか。さらには社会や環境、遺伝子も加味して依存を捉えるべきだが、従来の依存ではない依存の概念にはなんという名前をつければいいのか。
こうした新しい議論は、脳中心主義への批判と捉えることができます。それは哲学の分野でも起きていることで、人間はそんな単純なものではないという主張でもある。単純化したら捉えられない依存の現実が、さらなる議論をうながします。
(2024年9月12日)