認知症の発生率は時代とともに下がっている。だから過剰な心配をしなくてもいい。
そんなコメントが、米国医師会誌(JAMA)に掲載されました。認知症になるだろうと覚悟しているぼくにとっては、少し気の休まるコメントです(Dementia May Not Always Be the Threat It Is Now. Here’s Why. March 22, 2025. The New York Times)。
認知症の発生予測については、ことし1月、ネイチャー・メディスンという医学専門誌に載った研究が注目されました。
ニューヨーク大学のグループがまとめた研究は、アメリカ人の認知症は増えつづけ、2020年には51万4千人だったのが、2060年には約100万人になるだろうと予測しています。従来の予測を超え、高齢者や老人医療関係者に衝撃を与えました。
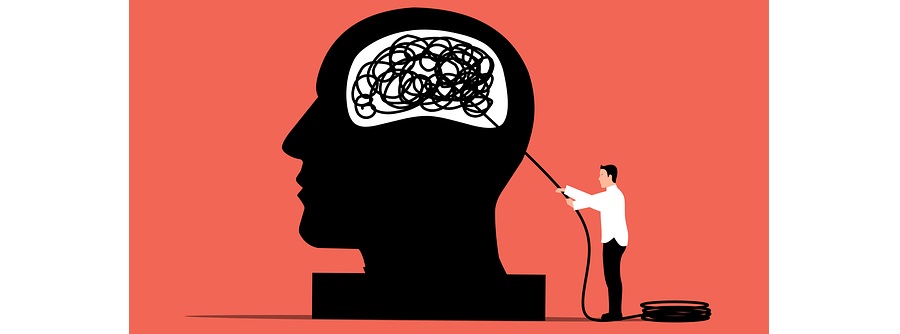
これに対し、デューク大学のエリック・スタラード博士らが反論のコメントをJAMAに寄稿しています。
スタラード博士らは、この40年、認知症の発生率は低下しているといいます。
たとえば、1905年生まれの人は85歳から89歳までに認知症になる割合が23%だったけれど、10年後に生まれた人ではその率が18%に下がっている。また1935年生まれの人は80歳までに11%が認知症になったけれど、1945年から49年生まれの人はその率が8%だった。
つまり時代が新しくなるほど、高齢者が認知症になる率は下がっている。デューク大学のムラリ・ドライスワミ博士はいいます。
「親の時代よりも子どもの時代のほうが認知症の発生率が少ないのなら、またその傾向がつづくなら、あの予測ほどに認知症が増えることはないだろう」
2060年に認知症が100万人ということはないだろう。

ではなぜ認知症の発生率は時代とともに下がっているのか。これについては諸説があるけれど、高学歴者が増えたことや喫煙が減ったこと、高血圧や高コレステロール、肥満や糖尿病の管理が進んだことなどが指摘されています。また補聴器が普及したことや、大気汚染が改善されたことを指摘するグループもある。
要するに健康で文化的な暮らしが認知症の発生を低下させる、ということらしい。
そういうことなら、ぼくも父親にくらべ認知症になる確率は低いのかもしれないと、わずかながら安心します。
でもそれはわずかでしかなく、大きな傾向は変わっていないからやはり覚悟はしておいたほうがいいかとも思う。
こういうのを一喜一憂というのだろうけれど。
(2025年3月28日)
