精神分析というものを、ぼくはずっと疑っていました。
そんなものでどう精神病に向き合えるのかと。きっと、ドラマや映画の精神分析に毒されていたからでしょう。カウチに横たわる患者が想念をしゃべり、精神科医が病気を解明するファンタジーです。そういうふりをする精神分析が多いらしい。
松本卓也さんの『人はみな妄想する』を読んで、ラカンの精神分析はまったくちがうことがじわりとわかってきました。
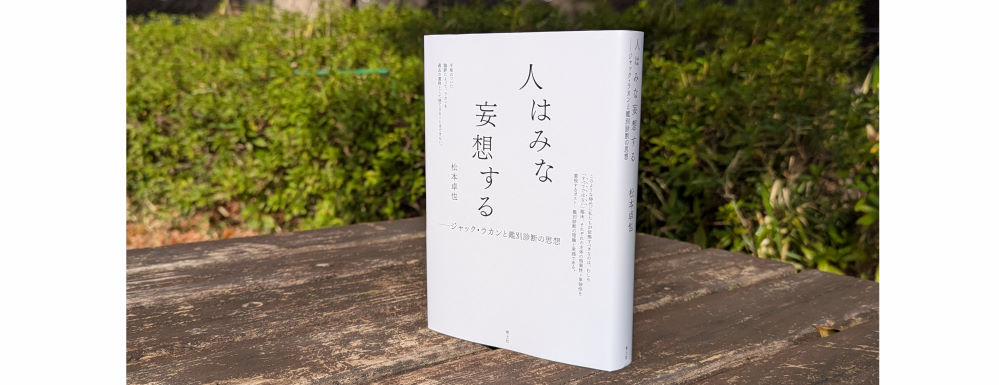
ほんものの精神分析は、ドラマとどうちがうのか。
患者がいうことを精神分析家が解釈するしくみは変わらない。しかし解釈はドラマとは正反対です。ラカンの考える解釈は、「意味を持ち」「説得的」であるようなものではないと、松本さんは指摘する。
「解釈とは、分析主体に対して、彼の人生や出来事に対する噛み砕いた明瞭な説明を与えることではないし、彼の症状に固定的な意味を与えて安心させることでも決してない。ラカンの考える解釈は「説明による安心」ではなく、むしろ「衝撃による動揺」をめざす」(185)
ピンとくるものがありました。
ラカンの精神分析は、精神病をわかりやすく説明しない。そもそも説明するためにおこなうものではない。分析するものとされるもののあいだで、予想外の事態が起きることを期待する。予想外の事態とは、突然語られたことばかもしれないし、ひらめきや連想、気づきかもしれない。予期しなかったものが表れ出たとき、人は動揺し、その動揺こそが変化への手がかりになる。そんなふうにぼくは読みました。
病気とがっちり固着した関係を、どうにかゆさぶろうとするのが精神分析ではないか。

この読みがどこまで妥当かはわからない。
しかしぼくはこれまで、北海道浦河町という精神医療の場で、「衝撃による動揺」が起きるのを何度も目撃し、あるいは目撃談を聞かされています。
たとえばある日ある患者が、病気がつらい、苦しいと訴えたとき、仲間が「まだ落ちきっていない、もっと落ちろ」とアドバイスしたのを見ています。いわれた患者は、え?と相手の顔を見ていました。その後、一時的ではあったけれど病気からの転機を経験しています。
精神分析ではないけれど、そこには「衝撃による動揺」がありました。
浦河の人びとはラカンも精神分析も知らなかったけれど、「衝撃による動揺」をくり返し日常の場で実現してきた。
精神病にどう向き合うかの実践において、ラカンの精神分析と浦河はつながっている。ぼくはそのことにピンときたのでした。
(2025年4月2日)
