若者が本を読まなくなった。
こんなことをいうと、あやしいと思われます。事実ではなくイメージ、それも誤ったイメージじゃないかと。
日本の若者だって、学校ではけっこう本を読んでいるという議論もある。その一方、町の本屋はどんどんなくなっているから、活字離れは現実でもある。
それがより鮮明なのがアメリカなのでしょう(There’s a Very Good Reason College Students Don’t Read Anymore. By Jonathan Malesic. Oct. 25, 2024. The New York Times)。
サザン・バプティスト大学のジョナサン・メイルシック教授が書いています。
2011年、授業で学生に9冊の本を課題として出した。ソローの『ウォールデン』やプラトンの『国家』などを読み、教室ではそれなりに活発な議論があった。しかし13年後のいま、自分は1冊の課題図書も出していない。読書に対する学生の意欲と能力の低下は、全国的にもいちじるしいものがある。

コロンビア大学のホロウィッチ教授が驚いたのは、学生が「1冊の本を最初から最後まで読みとおす」ことができないことでした。要約や引用ならまだしも、丸ごとは読めない。学生はいいます。高校でそんなの、したことなかった。
教授らのなげきは、学生が本を読む楽しみや知的な刺激を知らないだけではなく、大学がますます就職の準備機関になってきたことです。学生たちがあこがれるのはスター級のスポーツ選手かインフルエンサー。それがだめなら金融やコンサルティングの分野で有名企業に就職すること。読書なんかいくらしても金もうけにならない。必要ならAIがあるではないか。
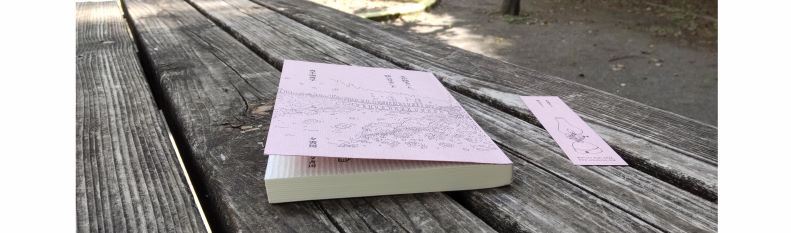
それでもなお、と、メイルシック教授はいいます。
すべての学生が時流に乗ろうとしているわけではない。そういう学生に対して私ができるのは、本には読む価値があり、読んで立ち止まり、考え、考え直し、さらに考えるために議論するのを助けることだ。彼らにチャンスを与えられればと思う。9冊は無理だけれど、新学期には1冊くらい課題図書を出したい。
むかし、アメリカの学生はよく本を読んでいると感心したものです。膨大な量を読み、授業で議論する。かなわないなと思ったこともあるけれど、いまわかるのは、力まかせの読書は知的な好奇心からではなく卒業証書のためだったということです。
一部の学生が自分の意志で本を選び取るようになったのは、むしろ健全な傾向ではないか。一律一様な読書なんてありえない。読みたい人だけが読むというのが活字離れの本態であるなら、新しい潮流として肯定したくなります。
(2024年11月25日)
