なぜガタリを読むのか。
もともとあったのは、精神病とは何かという問いでした。精神病はぼくらに何を問いかけているかという問いでもある。
その中心に、フェリックス・ガタリがいると思うようになったのは、制度的精神療法を知ってからです。
ちょうど1年ほど前、ぼくは制度的精神療法と出会いました。
20世紀はじめ、フランス南部の精神科病院にフランソワ・トスケルという精神科医がいた。彼は患者を解放し、芸術表現に向かわせるなど、前衛的な実践にとりかかったけれど、これが制度的精神療法と呼ばれるようになった。その歴史が去年8月、ニューヨークのアメリカン・フォーク・アート美術館で開かれた「アバンギャルド精神医学とアール・ブリュットの誕生」展で紹介されています。
まるで精神医療の革命であったかのように。
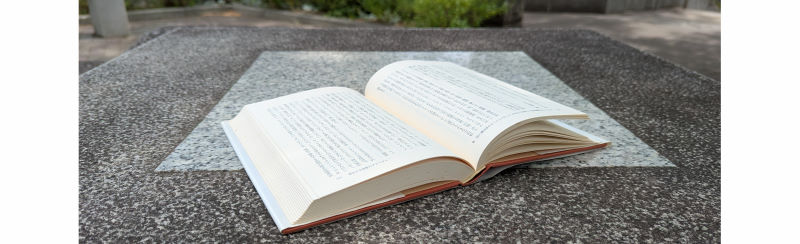
(原著は1980年。杉村昌昭訳、叢書・ウニベルシタス)
去年10月、北海道で開かれた「北海道精神科リハビリテーション研究会」でも、制度的精神療法が紹介されました。研究会のメインテーマではなかったけれど、基調講演のなかで精神科の重要な動きとして、松本卓也さんが言及しています。
精神医学に対する、ぼくのそれまでのイメージがくつがえりました。
ちゃんと調べたことなんてなかったけれど、なんとなく、イギリスの「反精神医学」やイタリアの「精神病院全廃」がこの分野の前衛だと思っていた。最近はフィンランドのオープンダイアローグのような新顔が現れた、という程度の認識でした。
そうではない。前衛はフランス現代思想だった。精神病ではなく、精神病を治療する制度、その意識と無意識、政治と社会、そうしたものを読み解こうとする制度的精神療法。ここにこそぼくらは目を向けるべきではないか。その中心のフェリックス・ガタリにこそ。

ガタリは、ジル・ドゥルーズとともに現代思想の最先端とされている。
けれどぼくから見ると、ガタリは哲学者より精神分析者です。精神科の「現場の人」です。精神病を通して「世界の裏側」にたどりつき、世界の裏側から、表側もまた別種の狂気に囚われた世界だと見抜いている。
狂気に鍛えられたガタリの経験と実践、思考と言語が、ドゥルーズとの「協奏」を「狂騒」に高め、現代思想の最先端を切り開いたのではないか。
ぼくのなかでは、ガタリは狂気の前で途方に暮れた人です。途方に暮れながらも、何をどうすればいいか、何を語ればいいかを考え抜いた。その経験と思考の断片に、わずかでも出会えないだろうかと、ぼくはガタリの痕跡をたどります。
(2025年7月9日)
