ノーベル文学賞を、とるとすれば彼女だろう。
川上未映子さんの『黄色い家』を読んで思いました。日本の作家ではよく村上春樹さんの名前が上がるけれど、川上さんは村上さんよりずっと今日性、世界性があるのではないか。彼女の作品から浮びあがる人間存在のよるべなさ、切実さに、読むものは何かを叫びたくなる。けれど何を叫べがいいかわからず、ことばを探しながらたたずんでしまう。
そんな作品に登場する人びとに、ぼくは精神科の現場で出会っていました。
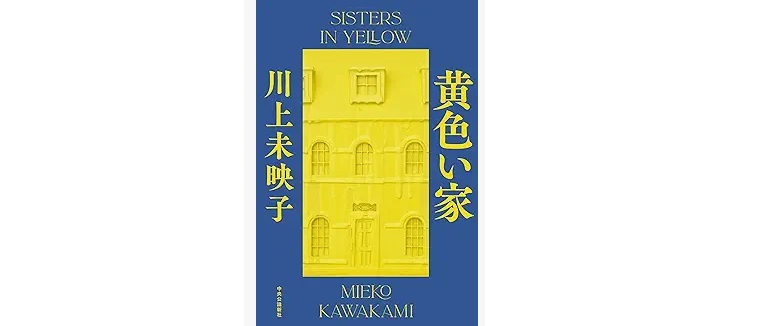
『黄色い家』は、主人公である若い女性と、彼女がともに暮らす3人の女性の話です。彼女たちのなかには、程度の差はあれ、また形はちがっていても、「あれ」がある。
あれって?
裏社会の映水(ヨンス)という男が、主人公とともに暮らす黃美子という女性について語るなかで出てきます。
「施設みたいなことを転々として育ったって、まあ珍しいことじゃないけど、どんな暮らしだったかは想像つくよな。食うもんがないとか普通だからな。それに、黃美子はあれもあるし、そうとう酷いめに遭ったはずだよ」
たとえば先のことが考えられない。金のことが考えられない。性格じゃなく、そういうやつが「学校とか・・・水商売とか闇とかそういう場所に」たくさんいただろ?
「身元も適当で、今日とつぜんいなくなっても、なんの問題にもならないようなやつな、そういうやつが夜にはたくさんいて、ある意味、物みたいになってんだよ」
世間には存在しないことになっている女たち。物たち。
「あれ」が何であるか、映水はいわない。
聞いている主人公も、じゃあ何々のことですか、とはいわない。作家もいわない。
いわないから、「あれ」が物語の命になる。
4人の女性が繁華街の片隅で懸命に働き、幸福に酔い、底辺に落ち、混乱と貧困、パニックのなかで消えてゆく。そこにつねにありつづけた、あれ。
知的障害だろうか。いやちがう。パーソナリティ障害でもない。「あれ」に精神疾患名はないし、そもそも精神疾患とはいえない。でも、「あれ」はある。ぼくは「あれ」が姿形を変え、たしかにあるのを、現実の世で多くの人びとのなかに見た記憶があります。
彼らは表社会から見ればなくてもいい存在であり、救いようのない落伍者です。『黄色い家』の主人公もそのひとり。けれど彼女は「あれ」になりきることもできなければ、人間の絆を捨てさることもできない。桎梏のなかで、ついには「あれ」から離脱している。表社会の人びとにはけっして訪れることのない人間の再生。稀有な世界性のある文学だと思います。
(2024年4月23日)
